

2025年4月22日

「できることなら歯は抜きたくない」
そんな想いを抱えて矯正相談に訪れる方が、ここ数年で明らかに増えています。
実際に、初診カウンセリングでも「抜かずに治療できますか?」という質問は非常に多く、矯正治療を検討する際の大きな関心事となっています。
では、なぜこれほどまでに「抜かない矯正」が求められるようになったのでしょうか?
その背景には、以下のような現代的な要因が複雑に絡んでいます。
マスクを外す機会が増え、SNSでの写真共有も当たり前になった今、「口元の印象」を気にする方が急増しています。
横顔のラインや口元の引っ込み具合に対する意識が高まる中で、「抜歯せずに整えたい」という願望が自然と広がっています。
「永久歯を抜いてしまったら後戻りできない」「健康な歯を抜くことに抵抗がある」
こうした感情は、誰しもが持つものです。特に健康意識の高い方ほど、「抜かずに治せるなら、できればそうしたい」と考える傾向があります。
私自身も「抜かずに治せるなら、できればそうしたい」と常に考えています。
「3ヶ月で前歯がきれいに並ぶ」「マウスピースで簡単矯正」──
一部のSNSや広告では、部分矯正があたかも“誰でもすぐできる手軽な治療”として紹介されることがあります。
しかし、部分矯正の適応症例は決して多くはなく、誤った期待を持ったまま治療を始めてしまうと、後悔につながるケースも少なくありません。
矯正治療は自費診療であるため、費用への不安から「できるだけ安く済ませたい」と考える方も少なくありません。
「抜歯を避けられれば費用も抑えられるのでは?」という想像が、“抜かない矯正”の人気を後押ししている側面もあります。
これらの背景から、「抜かない矯正」は確かに魅力的に映ります。
しかし、本当に非抜歯で成立する症例かどうかを正確に見極める“診断力”と、
安易な選択肢に飛びつかないための“患者自身の理解力と現実的な判断力”がなければ、
治療はむしろリスクの高いものになってしまいます。
“抜かずに整える”という選択肢は、正しく見極め、正しく選ぶことで初めて価値を持つものなのです。
歯を抜かない治療の“適応”とは何か?
マウスピース矯正は、近年の技術進化によってさまざまな歯の移動が可能になってきました。
歯を動かすための力の掛け方や方向、移動量、咬合への影響においてはワイヤー矯正と比較して制限もあり、すべてのケースに対応できるわけではありません。
特に「歯を抜かずに矯正する」場合、以下のような因子を慎重に評価する必要があります:
歯冠・歯根の形状
上顎洞や下顎管の位置と解剖学的余裕
骨格パターン(出っ歯・受け口・開咬・過蓋咬合など)
年齢や骨代謝の状況(成長期か成人か)
舌のサイズや口腔習癖の有無
既存歯の健康状態や補綴の有無 …など
これらの条件が複雑に絡み合っているため、
“抜かずに済ませる”ことを目的にするのではなく、“抜かずに安全に移動できる状態かどうか”
を見極めることが大切です。
マウスピース:清掃性が高く審美的、計画通りに動かすには患者の協力度と補助装置の工夫が必要。圧下、遠心移動、傾斜拡大が得意。
ワイヤー矯正:力のかけ方に自由度があり、特に垂直的(挺出)・回転的移動に強い。圧下、遠心移動、拡大は不得意。
補助装置:上記2つを組み合わせる際に必要な制御性と安定性を高める
実際の臨床現場では、マウスピース単独では困難な症例にも補助装置の併用により対応可能となるケースが多く、適切に設計すれば“抜歯せずに目的を達成する”治療も現実的です。一方ワイヤー矯正は、抜歯を余儀なくされるような症例において有効です。抜歯スペースは若干余ることが多く、臼歯の近心移動を必要とします。ワイヤーは最後臼歯の遠心移動を不得意とするため抜歯の選択が多くなりがちです。一方マウスピース(アライナー)は、最後臼歯を遠心へ移動することが可能です。
「補助装置を併用したマウスピース矯正」の成績については、現時点では質の高い大規模な研究報告が乏しいのも事実です。
2024年のEliasらによる系統的レビューでは、便宜抜歯を行った場合に唇の後退や臼歯間幅の減少が見られた一方、非抜歯群では治療期間の短縮や犬歯間幅の拡大が確認されました。審美的満足度や治療後の安定性には明確な差が認められなかったことも示されています(Elias et al., The Angle Orthodontist, 2024)。
また2023年のMota-Júniorらによるスコーピングレビューでは、抜歯・非抜歯のいずれの選択も個別の骨格的・審美的・機能的な目標に応じて選ぶべきとされており、後戻りに関しても両者にリスクは存在することが示されています(Mota-Júnior et al., AJODO, 2023)。
「気になるのは前歯だけだから、部分矯正で十分じゃないですか?」
このようなご相談は、20代〜50代まで幅広い年代の方から寄せられます。
確かに、軽度の叢生(歯の重なり)やすきっ歯など、限られた条件を満たす場合には部分矯正で十分な成果が得られることもあります。
しかし、当院での実績において、部分矯正が医学的に適応できる症例は、全体のおよそ2割以下に過ぎません。
なぜなら、「前歯だけの問題」に見えても、実際には噛み合わせのバランスや骨格的な要因が複雑に絡んでいるケースが多いためです。
部分矯正は、歯列の一部(主に前歯)だけを対象とした治療方法です。
「短期間・安価で済む」という印象が先行しがちですが、以下のような落とし穴も潜んでいます。
奥歯の咬合が不安定なまま前歯だけを動かし、噛みにくくなる
咬合高径(上下の高さバランス)が変化し、顎関節に負荷がかかる
正中線(上下の歯列の中心)がズレているのに前歯だけを並べようとしてバランスが崩れる
前歯の整列に必要なスペースを無理に確保しようとした結果、前方へ押し出すしかなくなり、口元の突出感が増してしまう
とくに「横顔を整えたい」「口元を引っ込めたい」といったご希望をお持ちの方には、部分矯正は適応外と考えるべきです。
その理由は、唇の位置やEライン(横顔のバランス)を整えるためには、顎全体の奥行きや骨格を含めた大きな移動が必要になるからです。
「安価な部分矯正」として広告される治療の多くは、治療にかける時間が極端に短いという特徴を持ちます。
しかし、矯正歯科において1ヶ月に動かせる歯の距離は、平均0.5〜1.0mm程度が限界です。
たとえば、唇を1mm下げるためには歯を3〜5mm動かす必要があるとされており、
これは歯の位置だけでなく、唇の厚みや軟組織の性質にも左右される繊細な変化です。
つまり、「見た目を少し整えたいだけ」のつもりでも、その実現には時間も計画も必要不可欠なのです。
早いのは動かす量が少ないことを意味します。少ない移動量の人はほんの一握りしかいないのが現実です。
前歯の並びに見える問題であっても、「上下の歯の中心がずれている」ケースでは、前歯だけでは調整できません。
中心線を揃えるには、奥歯の側方移動や、顎位そのもののコントロールが必要となり、
この場合は部分矯正では根本的な改善が不可能です。
見逃せないのは、歯周組織が弱っている場合の部分矯正リスクです。
とくに30代後半以降では、エストロゲンの低下や骨密度の変化によって、
歯周組織の防御力が不安定になることが報告されています(Payne et al., 1997 / Civitelli et al., 2002)。
また、歯周病の進行によって歯槽骨が減少しているケースでは、前歯が舌圧に耐えられず前方へ突出してしまうこともあります。
このような場合には、矯正よりも先に歯周病の管理と骨支持の回復を優先すべきです。
Mota-Júniorら(2023)のスコーピングレビューでも、抜歯か非抜歯か・部分か全体かの判断は「個々の状態と治療目標に基づくべき」と結論づけられています。
また、Eliasら(2024)のメタアナリシスでも、非抜歯群で治療期間が短縮する傾向があるものの、咬合や唇の後退などの面ではケースバイケースであると報告されています。
「前歯だけをきれいにしたい」というご希望は、決して間違いではありません。
しかし、部分矯正が可能かどうかの判断は、歯列全体のバランス・咬合・骨格・歯周状態などを総合的に診る高度な診断が必要です。
そしてもう一つ重要なのは、「費用の安さ」「期間の短さ」だけで判断しないこと。
一見安価でも、期待する結果が得られなければ、結局やり直しが必要になり、長期的にコストもリスクも高くなることを忘れてはなりません。
「歯を抜かずに矯正したい」と思ったときに最も大切なのは、どう診断され、どんな治療設計が組まれているかという点です。
マウスピース矯正が広まり、非抜歯での治療を希望される方が増えていますが、希望だけで治療が成り立つわけではありません。
大切なのは、本当に歯を抜かずに治療が成立するかどうかを多角的に診断し、無理のない計画を立てられているかという点です。
当院では、その診断と治療設計にこそ、最大の時間と労力をかけています。
咬合分析:噛み合わせのバランスや顎の運動、筋肉の緊張度を評価
レントゲン・セファロ分析:上下顎の位置関係や歯軸の傾き、スペースの余白を確認
口腔内写真・顔貌写真の記録:見た目と機能性の両面から総合評価
歯列模型やスキャンデータ:歯の形状・角度・アーチの広がりを立体的に把握
このような情報を総合的に分析することで、抜歯を回避する余地があるか、骨格や歯列の状態から正確に見極めることができます。
マウスピース矯正と一口に言っても、各メーカーによって動かしやすい歯の部位、精度、素材の特性、治療期間の管理方法などが大きく異なります。
当院では、10種類以上のマウスピースブランドの中から、患者さんの歯列・希望・治療のゴールに最も適したものを選定しています。
一つのメーカーしか使えない医院では、どうしても治療方法に制限がかかり、無理な移動計画を立てざるを得ないことも。
「抜かない矯正」を安全に成立させるためには、装置の選定力も不可欠な診断力の一部です。
さらに、マウスピース装置には以下のような得意・不得意な動きがあることも把握しておく必要があります。
▶︎得意な動き:
臼歯の遠心移動(ただし上顎洞に歯根が接していない場合)
歯の圧下(沈める動き)
▶︎不得意な動き:
歯の挺出(引き出す動き)
上顎前歯にトルクをかける動き(歯根を舌側に移動させる操作)
強い力を必要とする臼歯の移動(特に上顎洞に歯根が埋入している症例)
これらの特性を理解した上で装置を選定しなければ、歯列の崩れや不安定な咬合を招くリスクがあります。
症例によってはマウスピースだけではなく、ワイヤー矯正との併用を視野に入れる柔軟な計画設計が必要になることもあります。
たとえば、
一部の歯に強い回転移動が必要な場合
大幅な歯の挺出(歯を引き出す動き)を要する場合
骨格的な制限がある中で咬合バランスを保つ必要がある場合
このような症例では、ワイヤーの力を部分的に使うことで、全体の治療期間を短縮し、より精度の高い仕上がりを実現することができます。
当院にはワイヤー矯正の専門医も在籍しており、単独装置にこだわらず“結果を出すための最善の組み合わせ”を提案する体制を整えています。
「抜かないこと」が目的ではない。「歯を守ること」が目的です
最後に強調しておきたいのは、“抜かないこと”自体が目的ではないということです。
本来の目的は、機能性と審美性を両立し、できるだけ自分の歯を長く健康に保つこと。
必要なスペースが足りないにもかかわらず、無理に非抜歯にこだわった結果、
歯列が不安定になる
歯根に過度なストレスがかかる
咬み合わせが崩れる
という問題が起こることもあります。
当院では、「抜かずに済むならそうする」「でも、歯を守れないなら抜歯も必要」という、バランス重視のスタンスで診断と治療を行っています。
とはいえ、マウスピースを選択すると抜歯の確率は激減します。だから当院はワイヤーを第一選択にはしません。
しかし、症例によってはワイヤーの方が良い場合もあります。
それは抜歯適応のケースです。
当院のワイヤー専門医は、極力抜歯をしない方針で全力を尽くしています。
Robertson L, et al. Effectiveness of clear aligner therapy for orthodontic treatment: a systematic review. Orthod Craniofac Res. 2020 May;23(2):133–142. doi: 10.1111/ocr.12342
Rossini G, et al. Outcomes of clear aligner treatment: A systematic review. Angle Orthod. 2015 Nov;85(5):881–889. doi: 10.2319/061614-436.1
※上記の文献はすべてアライナー単体での歯の移動精度と治療効果に関する報告であり、補助装置(TADs・エラスティック・部分ワイヤー等)を併用した場合の治療成績は含まれていません。
実際の臨床では、こうした補助的アプローチの活用も含めた柔軟で現実的な設計力が求められます。
矯正治療を検討する際、どうしても見た目の変化や歯列の整い具合に意識が向きがちです。
しかし、治療中に見落とされやすい本質的なリスクとして、虫歯や歯周病の進行があります。
とくに30〜40代以降の方では、ホルモンバランスの変化や骨密度の低下などによって、歯周組織の状態が年齢相応に変化しやすくなる時期です。
そのため、若年層と同じ感覚で治療を進めると、思わぬトラブルを招くこともあります。
「前歯が出ているから、そこだけ治したい」というご相談は多いですが、前歯の突出感の原因が前歯そのものにあるとは限りません。
たとえば──
奥歯が舌側に倒れているために、前歯が相対的に前方へ押し出されている
歯周病によって歯槽骨が減少し、舌圧に耐えられなくなった前歯が唇側へと傾斜している
こうしたケースでは、単に前歯を引っ込める処置だけでは解決せず、奥歯の姿勢改善や歯周病の安定化が不可欠です。
歯周組織が安定していないまま歯を動かすことは、前歯の動揺や歯肉退縮をさらに進行させるリスクも孕みます。
このように、“見た目の問題”の裏には咬合や歯周組織の深層的な問題が隠れている可能性があるという視点が、診断・治療には欠かせません。
無料カウンセリングや、キレイラインサイト経由で予約された方の5500円の初回相談では精密検査はできません。
「何枚必要ですか?」この質問は正直なところかなりヤボな質問です。
『何枚ですか?』と初回相談時に聞くのはどうかおやめください。
まず大まかに『超軽度』、『軽度』、『中等度』、『重度』、『超重度』の5段階で評価します。
初回でご案内している簡易的なシミュレーション(←これを精密検査と呼んでいるクリニックも少なくありません)ではおおよその判定のみ。
実際の治療計画作成にはもっと詳細な検査と分析が必要です。
「私は何枚ですか?」ではなく、
「私の症状は軽度ですか?中等度ですか?それとも重度でしょうか?」ですね。
「前歯の見た目だけが気になるから、部分矯正で十分」と考える方は少なくありません。
しかし、当院の統計では部分矯正の適応が可能なケースは全体のわずか20%程度。
咬合バランスや歯周組織の状態を考慮すると、部分的な処置では対応できないことが多いのが実情です。
たとえば──
奥歯の咬合が不安定なまま前歯だけ動かした結果、噛みにくくなる
咬合の高さが変化し、顎関節に負担がかかる
前歯が整っても口元の突出感が改善されない
スペース不足を無理に補った結果、前歯が前方に押し出されてかえって突出感が増す
正中のズレを整えるには臼歯の移動が必須で、前歯だけで調整しようとすると歯列バランスが崩れる
特に、横顔の印象や口元を引っ込めたいといった審美的な希望がある場合、部分矯正では実現できません。
このようなご希望には、骨格や口唇・顎位の関係を総合的に評価した全体的なアプローチが必要になります。
マウスピース矯正は「清掃性が高い」とされますが、それは正しい使用・管理がなされていることが前提です。
以下のような状態では、むしろ虫歯や歯周病のリスクが高まります。
マウスピースを装着したまま間食する
装着前後のブラッシングやフロスが不十分
就寝前の清掃が疎かになる
こうした習慣があると、マウスピース内が密閉環境となり、細菌が急速に繁殖しやすい条件が整ってしまいます。
また、歯の移動中は歯列に一時的な物が挟まりやすかったり、歯が動くことによる清掃困難部位ができるため、炎症やポケット形成が進行するリスクも見逃せません。
この年代では、エストロゲンの低下や骨密度の変化によって、歯周組織の免疫応答が不安定になります。
とくに女性ではプレ更年期〜更年期にかけて、以下のような変化が現れやすくなります。
歯肉が腫れやすい
歯周ポケットが深くなる
歯槽骨が吸収されやすくなる
このような状態で歯を動かすと、歯根膜や骨に過度な負担がかかり、結果的に歯の寿命を縮めてしまう恐れもあります。
歯周病によって歯槽骨が吸収している状態では、歯は物理的な支えを失い、わずかな圧力でも移動や傾斜が進行しやすくなります。
これは、マウスピース矯正であっても例外ではありません。
そのため、歯を動かす前に歯周組織を整えておくことが絶対条件です。
当院では、歯周病が確認された場合には、矯正治療前に必ず歯周基本治療と細菌検査、必要に応じた生活習慣指導を実施し、炎症のない安定した状態をつくってから計画に入ります。
最後に強調したいのは、患者様の協力がなければ、どんなに優れた治療計画も意味をなさないということです。
マウスピースの装着時間を守る
毎日のブラッシング・フロスを徹底する
指導された生活習慣を実践する
少しの違和感でもすぐに相談する
この一つひとつが、治療の成功率と歯の健康寿命を大きく左右します。
「歯並びを整えること」だけでなく、「健康な状態を保つこと」まで視野に入れた矯正治療こそが、本当に価値ある医療であると、私たちは考えています。
「できることなら歯を抜かずに、きれいに歯並びを整えたい」
──これは、多くの方が自然に抱く願いです。
実際に、近年はマウスピース矯正の普及により、非抜歯で対応できるケースも増えてきました。
しかし、「歯を抜かない矯正=安全で確実な矯正」ではありません。
無理な非抜歯治療は、歯列の不安定化・咬合不良・後戻りのリスクを高める結果にもつながりかねません。
何より大切なのは、抜かずに済むかどうか”を的確に見極める診断力と、治療を支える予防力と管理力です。
どんな治療法にも限界があります。
だからこそ、私たちは 「抜かないこと」が目的ではなく、「歯を守ること」こそが本来の目的であると考えています。
本当に歯を抜かずに治療が成立するか
前歯だけで済むのか、それとも全体を診るべきか
歯周病や虫歯のリスクはないか
治療を支えるためのケア体制は整っているか
自分自身は日々の管理にどれだけ協力できるか
これらを一つひとつ丁寧に見極めたうえで、「抜かずに整える」矯正が可能かどうかを判断すべきです。
歯並びだけでなく、咬み合わせ、歯周組織、ライフスタイル、生活習慣、将来の健康寿命──
すべてを視野に入れたうえでの「非抜歯」という選択肢には、診断と支援の両立が欠かせません。
まずは、ご自身の状態を正しく把握すること。
そこから、“後悔のないスタート”は始まります。
無理なく歯を残すために、そして、
美しさと機能性を両立させるために──
デンタルサロンナチュール銀座では、
一人ひとりに合わせた診断と無理のない設計で、
矯正治療の選択肢をご提案しています。
ぜひ一度、ご自身のお口の状態を見つめ直してみませんか?
あなたにとって最善の矯正治療は、お買い物ではありません。
Q1. マウスピース矯正は本当に「抜かずに」できますか?
A. すべての症例で非抜歯が可能というわけではありません。歯列のスペース、骨格、咬合バランスなどを総合的に診断し、無理なく治療が成立する場合に限って非抜歯での矯正を行います。
Q2. 「前歯だけ整えたい」のですが、部分矯正は可能ですか?
A. 部分矯正の適応症例は当院の統計上およそ20%程度です。咬合や歯周の状態によっては適応外となる場合もあり、慎重な診断が必要です。
Q3. 矯正中に虫歯や歯周病が進行しませんか?
A. 適切な管理がなければリスクはあります。特にマウスピース矯正では、密閉環境となるため清掃不良がリスクを高めます。当院では、治療中のモニタリングとサポートを通じて管理体制を強化しています。
Q4. 40代でも矯正は可能ですか?
A. はい、可能です。30代〜40代はホルモン変化や骨密度の低下が始まる時期であり、歯周組織の状態も考慮して治療計画を立てる必要がありますが、診断と予防管理が両立できれば安全に治療可能です。
Q5. 抜歯ありの治療と、非抜歯治療で結果は変わりますか?
A. 無理な非抜歯計画は、歯列の安定性や咬合バランスを損なうことがあります。抜歯・非抜歯に優劣はなく、適応を見極めた上で安全な治療方針を立てることが最も重要です。
Elias, K.G., Sivamurthy, G., Bearn, D.R.
Extraction vs Nonextraction Orthodontic Treatment: A Systematic Review and Meta-Analysis.
The Angle Orthodontist. 2024; Volume 94, Issue 2.
DOI: https://doi.org/10.2319/030323-186.1
→ 抜歯・非抜歯治療間の歯列幅、唇の後退、治療期間などの比較を通じ、適応によって効果が異なることを報告。
Mota-Júnior, S.L., Giovanini, A.F., de Azevedo, V.E., Simões, R., Feres, D.B., Janson, G.
Extraction vs Nonextraction of Premolars for Orthodontic Treatment: A Scoping Review.
American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics. 2023; 164(1): 43–52.e1.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.ajodo.2022.08.016
→ 抜歯・非抜歯治療の適応、顔貌・安定性への影響、意思決定の臨床的根拠に関する包括的な文献レビュー。
Payne, J.B., Zachs, N.R., Reinhardt, R.A., et al.
The association between estrogen status and alveolar bone density changes in postmenopausal women with a history of periodontitis.
Journal of Periodontology. 1997; 68(1): 24–31.
DOI: https://doi.org/10.1902/jop.1997.68.1.24
→ 閉経後女性におけるエストロゲン低下が歯槽骨密度に与える影響を示し、歯周病との関係性を評価。
Civitelli, R., Pilgram, T.K., Dotson, M., et al.
Alveolar and postcranial bone density in postmenopausal women receiving hormone/estrogen replacement therapy: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial.
Archives of Internal Medicine. 2002; 162(12): 1409–1415.
DOI: https://doi.org/10.1001/archinte.162.12.1409
→ HRT(ホルモン補充療法)による歯槽骨密度の維持・改善効果を示し、閉経期女性の歯周環境への示唆を提供。
当院では、患者さんが抱えていらっしゃるお口のお悩みや疑問・不安などにお応えする機会を設けております。どんなことでも構いませんので、私たちにお話ししていただけたらと思います。
ご興味がある方は下記からお問い合わせください。
※自動音声でのご案内となります
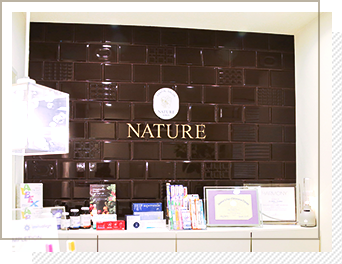
〒104-0061
東京都中央区銀座1丁目8−1 銀座池田園ビル8F
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前の部 | 休診 |
11:00〜 13:00 |
11:00〜 13:00 |
11:00〜 13:00 |
11:00〜 15:00 |
10:00〜 13:00 |
〜 |
休診 |
| 午後の部 | 休診 |
15:00〜 20:00 |
15:00〜 20:00 |
14:30〜 19:00 |
休診 |
14:00〜 18:00 |
〜 |
休診 |
【休診】 日・月・祝
日曜はオンラインのみ
©DENTAL SALON NATURE GINZA all right reserved.